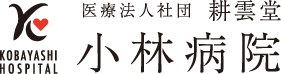身体的拘束最小化のための指針
身体的拘束等の適正化のための理念
- 身体拘束廃止に向けて最大限の努力を行わなければならない
- 身体拘束ゼロ及び看護の質向上を目指して実績を蓄積しなければならない
- 自信をもって提供できる医療を目指し、組織をあげて身体拘束廃止に取り組まなければならない
身体的拘束等の適正化のための基本的な考え
- 廃止に向けて常に努力を行わなければならない
- 安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない
- 身体的拘束を許容する考え方はやめるべきである
- 全員の強い意志で「チャレンジ」をする(看護ケアの本質を考える)
- 患者の人権を一番に考慮すること
- 医療サービスの提供に誇りと自信を持つこと
- 身体的拘束廃止に向けて創意工夫を講じること
- やむを得ない場合は患者・家族の方に対する十分な説明を持って身体的拘束を行うこと
- 身体的拘束を行った場合は常に廃止をする努力を怠らないこと(常に「0」を目指すこと)
身体拘束適正化のためのチームづくり
身体拘束最小化チームを設置し、次のことを検討する。
- 高齢者虐待・身体的拘束等に関する規程及びマニュアル等の見直し
- 発生した身体拘束の状況、手続き、方法について検討し、適正に行われているかを確認する。
- 虐待の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる
- 身体拘束に関する教育研修の企画・実施
- 日常的にケアを見直し、患者に対して人として尊厳のあるケアが行われているかを検討する
身体的拘束発生時の対応に関する基本方針
身体的拘束は行わないことが原則であるが、「緊急やむを得ない場合」については、以下の運用によるものとする。
- 「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件をすべて満たす場合に限り実施されるケース。
| 切迫性 *1 | 患者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い |
| 非代替性 *2 | 身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する看護方法がない |
| 一時性 *3 | 身体的拘束その他の行動制限が一時的なものである |
上記の3つの要素をすべて満たす状態であることを倫理委員会で検討、確認し記録しておくこと。
「緊急やむを得ない場合」の対応とは、これまで述べたケアの工夫のみでは十分に対処できないような、一時的に発生する突発事態のみに限定される。当然のことながら、安易に「緊急やむを得ない」ものとして身体的拘束を行うことのないようにする。
| *1 | 「切迫性」の判断を行う場合には、身体的拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える影響を勘案し、それでもなお身体的拘束を行うことが必要となる程度まで利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを、確認する必要がある。 |
| *2 | 「非代替性」の判断を行う場合には、いかなる場合でも、まず身体的拘束を行わずにケアするすべての方法の可能性を検討し、患者の生命又は身体を保護するという観点から他に代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要がある。また、拘束の方法自体も、患者の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならない。 |
| *3 | 「一時性」の判断を行う場合には、患者の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束的時間を想定する必要がある。 |
上記に該当する場合は身体拘束フローチャートに沿って行動実施し適宜評価すること
2025.4.14改定